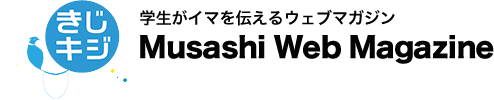アドミッションセンターってなんだ?

さて、次は寺岡部長へのインタビューです。

遠藤課長からいただいた、私からの二つ目の質問へのご回答に、「
高校生が大学に行って、その大学で授業を受ける、

高校生が大学で授業を受けることも、大学の先生が高校に行くこともあります。

そうなんですね。

高校で、いくつかの大学などが様々な分野の模擬授業を行って、高校生たちが自分の興味のある授業を聞くことで、「
武蔵大学に来ている依頼としては、

ということはつまり、かなり長い期間での体験になるんですかね。

場合によっては。

ですよね。


一年間通してやるっていうところも出てくるかもしれないし、
武蔵大学としてもそれをするのは初めてだったので、
受講者にとって、これがきっかけで大学受験につながるかもしれません。



あ〜

高大接続として行うこれらの事業への参加と、総合型選抜入試の受験を結び付けている大学も出てきています。

そういうことか。

自分の受験する大学がどんな勉強をするところなのかをきちんと理

それは、また新しいそのような枠を取るということでしょうか。

新しい枠として設定することもあれば、既存の枠の中で募集するという考え方もあります。

はい。

高校の授業と大学の授業を、もっと密接に結びつけて、

こういうのじゃなかった〜

そうですね。それが一番見やすい理由になります。
高大接続っていうと、さまざまな形がありますけど、

あ〜!

アドミッションセンターは、
高校生が1人で、あるいはお母さんや友達とかと複数で見学に来るケースと、

高校生が、団体で実際に来ているものですね。

そうです。そうやってまとまって来た高校生を、

そうすると、学習内容が想定と違ったということだけでなく、

そうです。また、さきほどの高大接続事業には、もう一つのやり方として、在学生に協力いただく大学もあります。

実際に、その大学に在学している人をということですか。

そうです。
例えば課題を出したものに対して、学生に説明をしてもらったりとか、学生と一緒に調べたりしてもらったりとか、学生に評価してもらうということもあったりするかもしれないし、最終的には先生たちがそれを協議、評価する、みたいな。
そういうようなことを、理系の大学で聞いたことがあります。

なるほど。
ちなみに、遠藤さんから頂いた回答に、新潟や北海道という単語が出てきますが、なぜこの二か所なのでしょうか。

北海道は、道外、道内へ進学する人が分かれるんですよ。
北海道を出る人は、全国各地へと進学します。
どうせ北海道を出るならどこへ行くにも一人暮らしになることにより、割と東京へと進学する人が多くなるんです。
そのような理由から、沖縄からや北海道から東京へ進学する方って結構多いんですけど、沖縄からはお呼びがかかることが少なくて。
なので、北海道へ向かっています。
新潟も、同様の理由です。あくまでこの二箇所を例として出しただけで、他にも長野だったりとか、静岡などへも向かっています。

そうなんですね。



寺岡部長、遠藤課長、取材へのご協力ありがとうございました!
取材協力:
アドミッションセンター
遠藤課長、寺岡部長
※所属・役職は取材当時
取材:
経済学部2年 ラムネ
経済学部2年 山口
社会学部2年 じゅん