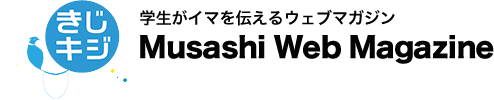【8号館空中庭園】武蔵ハーブプロジェクトを取材!【学生インタビュー】

〜時は流れ、5月某日〜
東京から電車に揺られること、約2時間。
千葉県北東部の某市にやってきました。

(駅に着いたし、連絡するか)

事前にお伝えした電車で、予定通り到着しました!

あ、今友達と川でナマズ釣ってるんで、もうちょっと待ってもらえます?

ナマズて…
ナマズが理由で待たされるの初めてだな。
しばらくしたのち…

お待たせしました〜
(クーラーボックスを開けて)
これ、釣ったナマズです!
今夜はこいつを唐揚げにしましょう!!

(いや、食うんかい)

駅から車で20分ほど走り、大塚さんが拠点にする古民家に到着しました。


これまでに何回か手が加えられているんですが、
建物自体は100年以上の歴史があるんですよ。


納屋もありますね。

敷地内には他にも、
井戸や汲み取り便所もあります。


↑汲み取り便所。さすがに使ってはいないらしい

このお家を含めた、広い範囲の土地を借りられていると聞きましたが、
具体的にはどのような土地ですか?

まずは、庭や納屋を含めた家の敷地。
あとは畑(一部は竹やぶ化)ですね。
のべ2000坪です。

↑竹やぶ付き物件


2000坪って、ちょっと想像がつきませんね。
※テニスコート(ダブルス)に換算すると、約25面分です
この暮らしを始めた理由

そもそもなんですが、
どうして千葉県の古民家で生活を始めたんですか?

始めから話すと、ちょっと長くなりますよ。
自分は古着が好きなんです。
それを仕事にしたいのはもちろん、古着をれっきとした文化にしたくて。
古着屋さんって、仕入れから販売まで個人で行っていることが多いんですよね。

たしかに、古着好きの方が個人で営業されているイメージがありますね。

そうなんです。
それはそれでいいんですが…
自分は、古着を売る人たちと買う人たちが集まる場や環境を創りたくて。

古着を愛する人たちが集う機会が増えることで、
文化として醸成されていきそうですね。

その通りです。
ただ、イベントを開催するって難しいことですよね。
出店してもらうにしても、お客さんを集めなくてはならないですし。
個人事業主に来てもらうからには、商売として成立する必要がありますからね。

関係者それぞれの立場を考慮して、
誰もが得をする場所を創る必要がありますね。

そこで、色々なイベントを企画して経験を積んでいるんです。
外に出かけていくことも多いですし、この家で行うこともあります。
古民家のリノベーションをしているのは、自分が住むためだけでなく、
〝何か〟をしたい人たちが集まれる場所を創りたくてやっています。


↑今はまだ、リノベーション中です

↑ピザ窯(の残骸)
自作したピザ窯でピザを焼きたい人と繋がり、ここでイベントを開催したそう。

様々な活動を通じて、最終的に自分がやりたい事(古着を文化にする)
の実現が近づいていく、ということですね。

意地悪な質問なんですが、都会でもイベントの開催や場所創りはできそうですよね。
なぜ、この場所を選んだんですか?

ある人が唱えていた「半農半X」という考え方に共感したんです。
地方に移住して農業を行い、生活コストを下げつつ食べ物は確保する。
そうしてできた余裕を、X(=自分のやりたいこと)に使う、というものです。

↑庭先を耕して、畑にしています

都会は生活コストが高いですから、
地方より高給でも、最終的に残るお金や余裕は少ないかもしれませんね。
武蔵大学についても聞いてみよう

…と、ここまで色々と聞いてきましたが、
きじキジの取材で来ていますので、武蔵大学に関しても聞いていきますね。

武蔵大学での印象的な出会いや出来事はありますか?

丸橋先生ですね。

やはり。親和性が高そうですよね。
【丸橋珠樹 教授】武蔵大学にいる理系の先生とは?
※丸橋先生は現在、武蔵大学の名誉教授となっています。
↑以前取材した記事はこちら。

白雉祭(武蔵大学の学園祭)で出会ったのがきっかけです。
Welcome! 白雉祭 ver.2022【70th ANNIVERSARY!】
↑白雉祭についてご存知ない方は、こちらの記事をご覧下さい。

学内を歩いていたら、ニコニコしているおじさんを見つけて。
「なんでニコニコしてるんですか?」って話しかけたのが出会いです。

話が盛り上がりそうな2人です。

盛り上がりましたね〜
特に、丸橋先生の「エディブル・キャンパス」という考えに共感して。
※エディブル(edible)=食べることのできる・食用の

せっかく緑豊かなキャンパスですから、
食べられるものが多い方が面白いですよね。
【たんぽぽコーヒー】君は武蔵の味を知っているか〜前編〜
【3号館屋上】江古田ミツバチプロジェクト
↑これまでにも、色々と食べてきました

ゆくゆくは、この家の周囲を食べられる植物でいっぱいにしたくて。
来週には夏野菜を植えるので、収穫期には味噌とマヨネーズを片手に、
庭ビュッフェをしてもらおうと思ってます。

【ビュッフェ会場、庭】

武蔵ハーブプロジェクトも、丸橋先生から教えてもらったんですよ。
何かをつくるのが好きなので、大学でもできるのは良いと思って。

この前、空中庭園でキイチゴの実を食べてましたよね。大量に。

まあ、食べられるものがいちばん好きですね。
(一同笑い)

武蔵大学の自然科学分野の事務員さんたちにも、親切にしてもらってます。
例えば、これ。


藍(あい)です。藍染に使う。
授業で使うために育てていたらしいんですが、余りをいただいて。
大切に育ててます。
その他にも、研究室の片付けで出てきた植物の種をもらいました。

人どうしの距離が近い、武蔵大学らしいエピソードです。


時間も時間ですし、そろそろナマズ食べますか?

あ、覚えてました?

↑さばいたナマズは、唐揚げにしました

↑大塚さんのお友達も交えて、数人でいだたきます
付け合わせは、自家製サニーレタスです。

それじゃ、ゲームで食べる順番を決めましょう。

(どうして罰ゲームっぽくなってるんだ)
![]()
…気になる感想は…
(参加者のAさん)食べた瞬間に「ドブ臭い!」と感じたそう
(参加者のBさん)「下味が濃すぎて、ナマズの味がわからない」
(よこた)「意外と美味しいかも。クセのない白身魚のように感じた」
身の部位や下処理によって、味の差が大きいようですね。
![]()
次の日は田植えとのことで、参加させていただきました。

↑もちろん手で植えます

↑おそらく、武蔵大学でいちばん田んぼが似合う男

↑田んぼからの帰り道で出会ったキジ。運命を感じる


武蔵ハーブプロジェクトから、思わぬ方向に進んだ今回の取材。
取材を通じて改めて感じたのは、大学での人の距離の近さです。
個性豊かな学生と教職員との距離の近さが、武蔵大学の魅力かもしれません。

取材協力:武蔵大学 武蔵ハーブプロジェクト
大河原さん
若菜さん
大塚さん
大塚さんのご友人方
取材・撮影・執筆:人文学部4年 横田